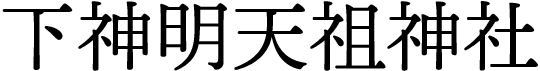神棚は、神社で受けられたお神札をおまつりする神聖な場所です。
神棚をおまつりすることは、ご家庭の守り神としてお鎮まり頂く事であり、ご家族の皆様で神棚に手を合わせることで益々に神さまのお守りをいただけることでしょう。
神棚のまつり方とお参りの仕方
生活の中心となる部屋の清浄な場所を選び「南向き」または「東向き」にまつります。(建物の事情により、やや南向き、やや東向きでも構いません)お参りの仕方は「二拝二拍手一拝」です。
朝には家族の健康と安全を願い、夕べには平穏無事に一日を過ごせたことに感謝します。
また、お祝いごとのあったときなどは、神棚にその喜びをお伝えし、神の恩恵に感謝してお参りしましょう。
神棚がない時は
タンスや棚など、目通りの上のところを綺麗にしておまつり下さい。
本来、お米、お酒、お塩、お水、お榊などをお供えしますができる範囲で行い、日々感謝の祈りを捧げましょう。ご不明なことがあれば、お気軽に神社へお問い合わせ下さい。
よくあるご質問
【質問1】なぜ神棚のお神札を一年ごとに新しくするのですか?
神道には「常若(とこわか)」という信仰があります。常に新しく若々しく瑞々しくいられますようにとの祈りです。
全てが新たまるお正月を迎えるにあたり、お神札を新しくすることは、より神さまのお力をいただくことであり、私たちの気持ちも新たにしていくことなのです。
【質問2】神棚に氏神様のお神札だけでなく、皇大神宮(お伊勢様)のお神札もお祀りするのはなぜですか?
皇大神宮(内宮)は、国家国民をお守りいただく日本の総氏神さまと言えます。
一方で、お住まいの地域にある神社は、地域氏子をお守りいただく氏神さまです。
このように役割が異なるので、皇大神宮と氏神様の両方をおまつりします。
【質問3】年末に家族が亡くなりました。新しいお神札は、いつから神棚に祀ったらよいでしょうか?
家にご不幸があった場合、神棚の前面に半紙などの白紙を貼り神事を慎みます。
忌明けは一般的に五十日を目処にしますので、その際に白紙を取り、新しいお神札をおまつり下さい。
尚、お祝い事もその間は喪(忌)に服し、お慎み下さい。
【質問4】御祈祷でいただいた木のお神札は宮型に入りません。どうしたらよいでしょう?
宮形の左右におまつり下さい。また、左右に場所がない場合は、正面を避け宮型に立て掛けておまつり下さい。
【質問5】「天」や「雲」と書いた紙を神棚の上の天井に貼るのはどんな意味があるのでしょうか?
現代の家庭はマンションや二階建てが多く、尊い神様をおまつりした神棚の上を階上の人がやむを得ず踏む場合があります。
これはあまりに恐れ多いということから、せめて「天」や「雲」と書いた紙を貼って「神棚より上は天上であり雲上であって他には何もありません」と、神様にお許しをいただこうという心情を表したものです。
【質問6】お神札にかけてある薄紙は剥がしてからお祀りするのですか?
薄紙はお神札を宮形に納めるまで手の汚れや他の穢れなどに触れないようにするためのものです。
したがって、宮形に納める際には薄紙を剥がして下さい。
もちろんお神札を扱うときは、手を洗い口を濯(すす)ぎ、できる限り身も心も清浄かつ平静であるように心掛けましょう。
【質問7】一年間お祀りしたお神札はどのようにしたらよいですか?
過去の一年が無事過ごせたことを感謝し、神社にお礼参りをして納めます。このお神札は神社でお焚上げされます。
上記、ご質問にないお問い合わせはこちらから
プライバシー・ポリシー(個人情報保護に関する基本方針)について